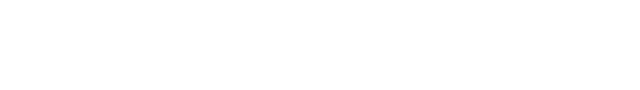緑内障に対する点眼治療
緑内障点眼の考え方
緑内障は目の奥の視神経が徐々に傷害され、視野が欠けてくる病気です。原因として最も主要なものが、「眼圧」であると考えられています。
眼圧は日本人では20mmHgを超えると異常値とされています。
眼圧の高い緑内障のみならず、日本人に多い、眼圧の正常な緑内障(正常眼圧緑内障)に対しても、眼圧を下げる治療が最も効果的です。
眼圧を下げる手段として、一般的にはまず点眼治療を行います。
眼圧下降の目標として、初期の緑内障では19mmHg以下、中期では16mmHg以下、後期では14mmHgが推奨されます。また、治療開始前のベースライン眼圧よりも20〜30%の眼圧低下という目標も提唱されています。(緑内障診療ガイドライン第5版)
緑内障点眼薬の作用する仕組み
眼内には「房水」という液体が循環しています。房水は、毛様体で産生され、後房から瞳孔を通って前房に達し、その後隅角から眼外に排出されます。この房水の、産生と排出のバランスで、眼圧が保たれています。
眼内から眼外への房水の排出経路は主経路と副経路の2つがあります。主経路は、線維柱帯からシュレム氏管を通り、上強膜静脈から眼外へ出る経路です。副経路は隅角・虹彩根部から毛様体筋を経て排出される経路で、経ぶどう膜強膜流出路ともいわれます。
緑内障点眼
現在では下記のように多種の緑内障点眼薬が使用されています。第一選択薬としてはプロスタグランジン製剤、EP2受容体作動薬、β遮断薬のいずれかを選択することが多く、一剤では効果不十分な場合、その他の薬剤を組み合わせて使用します。薬剤ごとに点眼回数が決まっていますので、しっかりをそれを守ることが大切です。近年は2種類の緑内障点眼を組み合わせた合剤も種々開発されています。
主な緑内障点眼薬(単剤)
| 一般名 | 先発薬 | 特徴、注意点 | |
|---|---|---|---|
|
FP受容体作動薬 作用:副経路 |
ラタノプロスト |
キサラタン |
|
| トラボプロスト | トラバタンズ | ||
| ビマトプロスト | ルミガン | ||
| タフルプロスト | タプロス | ||
|
EP2受容体作動薬 作用:副経路+主経路 |
オミデネパグイソプロピル | エイベリス |
|
|
交感神経β遮断薬 作用:房水産生抑制 |
マレイン酸チモロール | チモプトール、チモロール |
|
| 塩酸カルテオロール | ミケラン | ||
|
交感神経α2刺激薬 作用:房水産生抑制+副経路 |
ブリモニジン酒石酸塩 | アイファガン |
|
|
ROCK阻害薬 作用:主経路 |
リパスジル塩酸塩 | グラナテック |
|
|
炭酸脱水酵素阻害薬 作用:房水産生抑制
|
ドルゾラミド塩酸塩 | トルソプト |
|
| ブリンゾラミド | エイゾプト |
|
緑内障点眼薬(合剤)
| 一般名 | 先発薬 | |
|---|---|---|
| FP作動薬+β遮断薬 | ラタノプロスト+チモロール | ザラカムまたはラタチモ |
| ラタノプロスト+カルテオロール | ミケルナ | |
| トラボプロスト+チモロール | デュオトラバまたはトラチモ | |
| タフルプロスト+チモロール | タプコムまたはタフチモ | |
| 炭酸脱水酵素+β遮断薬 | ドルゾラミド+チモロール | コソプトまたはドルモロール |
| ブリンゾラミド+チモロール | アゾルガ | |
| α2刺激薬+β遮断薬 | ブリモニジン酒石酸塩 +チモロール | アイベータ |
| α2刺激薬+炭酸脱水酵素阻害薬 | ブリモニジン酒石酸塩 +ブリンゾラミド | アイラミド |
| ROCK阻害薬+α2刺激薬 | リパスジル塩酸塩+ブリモニジン酒石酸塩 | グラアルファ |