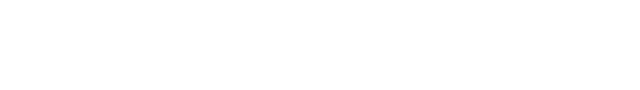結膜の病気
結膜下出血
白目の一部あるいは全体が鮮明に赤くなります。原因は、結膜の血管からの出血で、こすったり物が当たったりといった外的要因によるもの、いきんだり嘔吐などによる血圧上昇によるもの、あるいは特に原因のないものがあります。
特に治療は不要ですが、違和感が強い場合は点眼薬を処方する場合もあります。繰り返し起こる場合は、あとに述べる「結膜弛緩症」が原因の場合があり、手術治療で改善することもあります。
アデノウィルス結膜炎
流行性角結膜炎(EKC)や、咽頭結膜熱(PCF)などを起こすアデノウィルス感染症です。症状はめやに、充血、かゆみなどが強く、また感染力が非常に強いため、保育園や入院病棟などで集団発生することがあります。アデノウィルスは2本鎖DNAウィルスで多数の型があります。
当院では迅速診断キットを用いて診断を行います。所要時間は7分間です。
ウィルスに対する直接の治療はありませんが、症状をやわらげ、混合感染を予防するため、炎症止めの点眼薬を使用します。
アレルギー性結膜炎
さまざまな物質によるアレルギー症状として、目のかゆみ、充血、眼脂などを生じます。時期によって季節性あるいは通年性などに分類されます。スギやヒノキ花粉が原因となるものを花粉症と呼びます。また、コンタクトレンズを装用している方では、レンズに付着したたんぱく質などの汚れに対するアレルギーも起こり得ます。これらのアレルゲンが原因となって、結膜のマスト細胞からヒスタミンが放出されることによって、症状が生じます。
治療としては、抗アレルギー点眼の使用が基本ですが、症状が強い場合は、ステロイド点眼を短期間使用することがあります。また、アレルギー性鼻炎を併発している場合には、内服薬を併用することもあります。
春季カタル
若年者に多い、アレルギー性結膜炎の重症例で、結膜に増殖性変化を認めるものです。増殖病変の場所によって、(角膜)輪部型と眼瞼(結膜)型に分けられます。輪部型では、角膜と結膜の境目に堤防状の盛り上がりを認め、眼瞼型では、瞼の裏の結膜に、巨大乳頭を形成します。
治療としては、抗アレルギー点眼のみでは不十分なため、ステロイド点眼を使用します。その際、若年者ではステロイド点眼に反応して眼圧が上がることがあるので、眼圧の測定が必要です。近年では、眼圧上昇のリスクのない免疫抑制剤を使用することが多くなっています。
結膜弛緩症
加齢やコンタクト装用により白目の結膜が弛緩し(ゆるみ)、ひだやしわとなるために、異物感や流涙、ドライアイ症状を生じます。しわの部分の血管から結膜下出血を繰り返すケースもあります。軽症例では点眼薬で様子をみますが、改善しない場合は手術を行います。当院では、結膜焼灼法と結膜切開法の2種類の手術を行っております。焼灼法は、結膜の余剰部分を電気メスで焼いて短縮する方法です。切開法では、結膜を舟状に切開し、余った部分を切除したのちに縫合します。いずれの方法を用いるか、症状や弛緩の程度を考慮して決定しています。
翼状片
しろ目(結膜)がくろ目(角膜)に侵入する病気です。多くは鼻側に認められ、紫外線の関与が強いといわれています。大きくなると角膜をひっぱり、不正乱視を起こします。手術では、翼状片を角膜からはがして切除し、結膜を再建し、縫合します。数%の方に再発のリスクがあります。再発例に対しては、当院では0.025%マイトマイシン溶液の塗布を併用した手術を行っております。